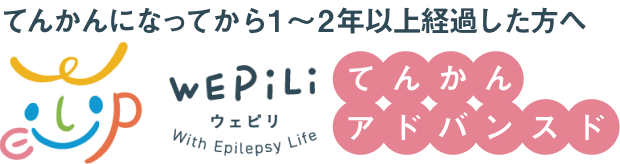内科的治療とは、てんかん治療に習熟した医師が2年間治療してもおさまらないてんかん(お子さんの場合では1年の場合も)の場合に行う事が多い、内服薬の種類や量を調整する治療のことです。
このぺーじでは、内科的治療についての情報をQ&A形式でご紹介します。
発作がコントロールできない時の内服薬整理方法は?
てんかんでは1つの内服薬で発作が十分に予防できなければお薬を追加し、2〜3種類を組み合わせて治療することもありますが、薬の種類が多くなると...
前頭葉てんかん、夜間発作は薬で止まる?
夜間の前頭葉てんかん、睡眠中の発作は日中の眠気や日常生活に影響するため心配ですね。一般的に60-70%の発作は抗てんかん発作薬で止まるとされていますが...