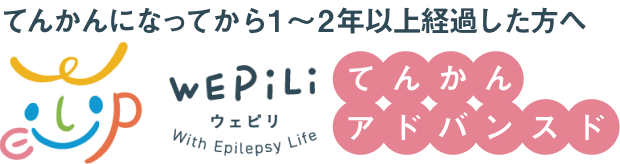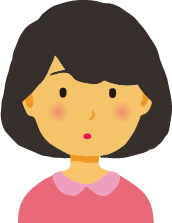
点頭てんかん(ウエスト症候群)の検査にはどのようなものがありますか?

脳波検査は言うまでもなく重要で、診断や治療効果判定に使用します。約30分-1時間程度の短時間の場合もあれば、1泊2日など入院して行う長時間ビデオ脳波検査を行う場合があります。目的に応じて使い分けます。
次に脳の構造を調べる検査として、頭部CT・頭部MRIを行います。頭部CTでは、出血や石灰化を検出することができ、検査時間が短時間であることが利点ですが、検査時にわずかに放射線を利用する点が欠点です。一方、頭部MRIは、脳の構造を「脳のしわの形」まで詳細に見ることができ、検査時に放射線を使用しませんが、撮影時間が30分程度(もしくはそれ以上)必要とします。
脳の機能を見る検査としてSPECT・PETという検査をする場合があります。SPECT(脳血流)は、“脳の血流の分布”を映し出す検査です。発作のない時(発作間欠期)にはてんかん焦点は集積が低下します。発作をしている時(発作時)にはてんかん焦点は集積が上昇します。また発作時-発作間欠時の血流の差分を取ることで、より明瞭なてんかん焦点を見つけることができる場合があります。FDG-PETでは “脳のブドウ糖代謝の分布”を映し出す検査で、脳血流と同じようにてんかん焦点は集積が低下します。これらの検査によりMRIで異常がない場合でもてんかん焦点を同定できる場合があります。また、脳の機能を推測できたり、てんかん焦点をより確実にすることができるなどが期待できます。
その他、原因を同定するために、血液・尿検査、髄液検査、代謝検査、染色体検査や遺伝子検査を行う場合があります。