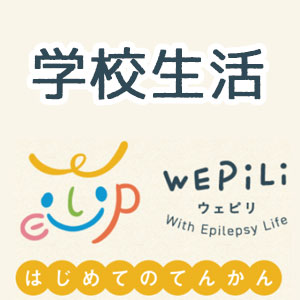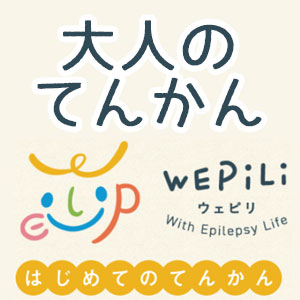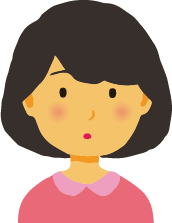
園や学校における発作時の対応について教えてください

学校におけるてんかん発作時の坐薬挿入については、平成28年2月29日付けで文部科学省による規定があります。学校現場等で児童生徒がてんかんによるひきつけを起こし、生命が危険な状態等である場合に、現場に居合わせた教職員が、坐薬を自ら挿入できない本人に代わって挿入する行為については、以下の4つの条件を満たす場合は、医師法第17条(医行為)の違反とはならないとされています。
- 事前に医師から書面で指示
- 学校・教育・保育施設等に対して具体的に依頼
- 本人確認し、手袋を装着し坐薬挿入
- 坐薬を使用した後、必ず医療機関を受診
また教育・保育施設等(保育園、幼保連携型認定こども園、放課後児童健全育成事業、放課後子供教室等)におけるてんかん発作時の坐薬挿入についても、現場に居合わせた教育・保育施設等の職員又はスタッフが行う場合は同様とされています。一連の行為については、プライバシーの保護に十分に配慮するよう明記されています。
■書面による医師からの指示書の作成方法
「学校や園での緊急処置について」の項目で、学校および教育・保育施設等におけるてんかん発作時の坐薬挿入について記載いたしました。各自治体によって、フォーマットは異なります(例えば、大阪府のものは こちらで確認できます)。
記載は医師が行う必要があります。受診の際に、医師に記載してもらうように依頼します。発作時に現場での複雑な判断が必要にならないように、できるだけシンプルなものが望まれるので、主治医と相談しておきましょう。現時点では、発作時に使用される薬剤としては、ジアゼパム坐薬(※)が多く、その他、エスクレ坐薬なども使用されています。欧米では、即効性のあるジアゼパムゲル製剤やミダゾラム頬粘膜製剤などが使用されています。
(参考)ジアゼパム坐薬(ダイアップ坐薬🄬)について
けいれん重積治療ガイドラインには、ジアゼパム坐薬に関して、以下の記載があります。
「日本での効果・効能は「熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善」である。発作予防に対する有効血中濃度(>150-350ng/ml)に達するのは投与後30分以内であり、8時間間隔で2回挿肛することで予防治療域濃度を24時間保てる。急性けいれん発作発症後に治療として使用した報告は少なく、目前のけいれんを収束させる適切な使用量(けいれん発作収束が期待される血中濃度は、発作予防に対する濃度より高いことが推定される)、有効性のエビデンスはない。挿肛後ピーク濃度に達するまでの時間が遅いため、救急治療目的には適さない。」
つまり、ジアゼパム坐薬は、効果が出るまで少なくとも15-30分以上かかると推定されるため、目の前で生じている発作を速やかに消失できる効果は期待できないと考えられています。しかし、病院搬入まで時間を要するような場合などで、発作の群発を防ぐ、搬送中に発作を収束させる、病院搬送後の治療に繋げる、などの可能性があります。総務省の公表では、救急要請から病院搬入までの平均所要時間は約40分とされていますので、現状ではジアゼパム坐薬の効果と限界を踏まえて使用する必要があります。
参考資料
小児けいれん重積治療ガイドライン2017 小児神経学会 ダイアップ坐剤添付文書
総務省ホームページ
大阪府教育庁ホームページ