目次:
1.てんかん診断までの流れ
2.問診・診察で行うこと
3.てんかんの検査の種類
4.脳波検査について
5.てんかんの検査・診断に関連するQ&A
てんかん診断までの流れ
てんかんの診断および治療の開始は一般的に以下の流れで行われます。
- 問診・診察
- 検査
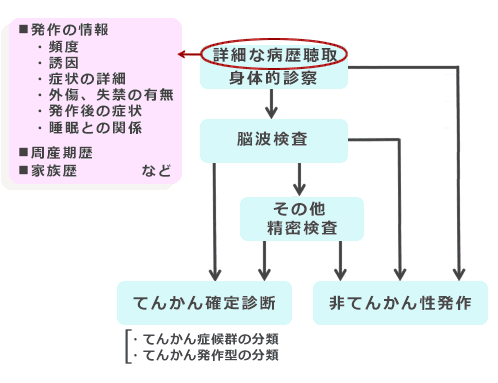
問診・診察で行うこと
問診では以下のような発作の情報をお聞きしたり、身体的診察を行います。
- 頻度
- 誘因
- 症状の詳細
- 外傷、失禁の有無
- 発作後の症状
- 睡眠との関係
- 周産期歴
- 家族歴
など
最近ではスマートフォンの普及により、発作の様子が録画されている場合があり、患者-医療者間で視覚的に共有されるようになってきました。また、身体診察により、てんかんの原因となる体質や病気がわかる場合があります。
てんかんの検査の種類
治療方針を決めるために、以下の精密検査を行う場合があります。検査によっては入院が必要です。以下のような検査を行うことがあります。
■血液・尿検査
てんかんの原因となる病気が体に隠れていないかをみるために、血液検査、尿検査を行います。低血糖、カルシウム不足、電解質異常の確認に加えて、染色体検査、遺伝子検査を行う場合があります。てんかんの種類によっては髄液検査をすることがあります。てんかんの薬を飲んでいる時は、副作用のチェックとして、血液検査・尿検査を行います。また、必要に応じて薬の血中濃度を確認します。調子が不安定な時は毎週することもありますが、安定している方は年に1~2回程度です。

■ビデオ脳波同時記録
発作が起きている瞬間の脳波をみるには、脳波検査を行いながら、ビデオも同時に記録し、発作のタイミングを確認することが多いです。入院で行う必要があり、半日から数日間、保護者付き添いのもと病院で過ごしてもらう必要があります。

■頭部CT-MRI
CTでは脳の構造に加え、石灰化・出血などをみることができます。MRIでは脳の構造を詳細に見ることができ、てんかんの原因がないかを探します。
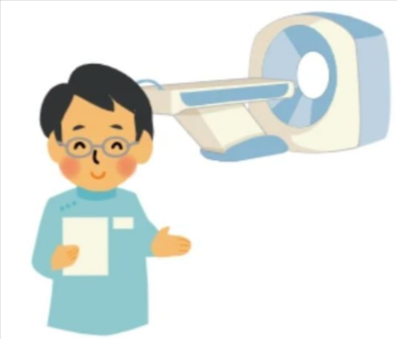
■脳核医学検査(SPECT・PET)
脳の血流分布(発作の無い時、発作の時)、神経受容体の分布、糖の代謝分布などを評価し、てんかん焦点を見つけます。
■神経心理検査
知能検査や発達検査により、言語機能・認知機能・記憶力などの得意・不得意を評価します。
脳波検査について
脳波検査は、外からはみえない脳の活動をみるてんかんの診断、治療には欠かせない検査の1つです。
診断時には、脳波を確認することで、てんかんをどの程度疑うかの判断材料の一つにしたり、てんかんの種類を診断するのに役立ちます。治療過程では、治療の効果判定や治療中止の判断材料になることがあります。
脳波検査の流れ
てんかんの検査には、外来で行う検査と入院して行う検査があります。
■外来の場合(脳波検査)
≪目的≫
普段(発作ではないとき)の脳の活動状態を確認します。
≪時間≫
30分~1時間
≪注意事項≫
眠るお薬を使うことがあります。検査後のふらつき、転倒にご注意ください。

■入院の場合(ビデオ脳波同時記録)
≪目的≫
実際のてんかん発作(発作疑いの動作)時の脳波をビデオと同時に記録することで、てんかん発作かどうか、発作であれば発作が出現する場所とその広がりを確認します。
≪時間≫
半日~数日間
≪注意事項≫
抗てんかん薬を減らすことがあり、いつもより大きな発作が起きることがあります脳波電極を長時間皮ふにつけるため、低温やけどや皮ふのかぶれが出ることがあります。

脳波検査でわかること
脳波検査は、外からはみえない脳の活動をみるてんかんの診断、治療には欠かせない検査の1つです。
診断時には、脳波を確認することで、てんかんをどの程度疑うかの判断材料の一つにしたり、てんかんの種類を診断するのに役立ちます。治療過程では、治療の効果判定や治療中止の判断材料になることがあります。
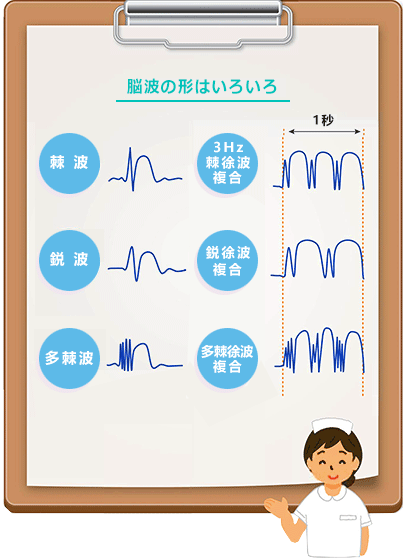
てんかんの検査・診断に関連するQ&A
12歳娘の朝の頭痛や怠さ、自律神経失調症で検査は本当に不要?
起立性調節障害の好発年齢は10~16歳で、 有病率は、小学生で5%、中学生で10%と、中学生に上がる時期に発病する方も多くおられます。
非定型良性小児部分てんかん(ABPE)とはどういったものか?
ABPEは非定型良性小児部分てんかん(atypical benign partialepilepsy)の略語で、覚醒時に力が抜けるような症状…
