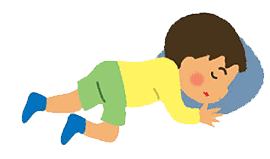主に乳児や幼児が高い熱(特に38度以上)を出した時におきるけいれんを「熱性けいれん」と呼び、原因はお子さんの未熟性や体質によるものではないかとされています。
わが子がけいれん(ひきつけ)をおこしているのを経験されると、親は非常に驚き、そして心配される事だと思いますが、けいれんは短時間で収まることが多く、大きくなければ特に問題なく過ごされることが多いとされています。
ただし、この中に「てんかん」発作が混じっている事があります。どの病気もそうなのですが、最初は病気と区別がつかないことがみられるため、時には慎重な対応が必要です。乳児期(1歳まで)に熱性けいれん(しばしば重積)や入浴時のけいれんが繰り返して出現し、熱のない発作がでてくるドラベ症候群というてんかんがあります。乳児期には、てんかんと診断することはしばしば困難です。詳しくは、「お風呂の時のけいれん」を参考にしてください。
それでは熱性けいれんに関するみなさんの質問と先生からの回答を読んで、熱性けいれんがどういうものなのかを理解していきましょう!
目次:
1.熱性けいれんとは
2.熱性けいれんの種類
3.けいれん時の対応
4.病院の受診について
5.熱性けいれんの原因
6.熱性けいれんに関する検査
7.予防について
8.後遺症の可能性
9.てんかんの可能性
10.熱性けいれんに関連するQ&A
熱性けいれんとは
熱性けいれんガイドライン2015には、「主に生後6-60か月(満5歳)までの乳幼児期に起こる、通常は38度以上の発熱に伴う発作性疾患(けいれん性、非けいれん性を含む)で、髄膜炎などの中枢神経感染症、代謝異常、その他明らかな発作の原因が見られないもので、てんかんの既往のあるものは除外される。」とあります。
熱性けいれんは、日本ではこども全体の8-10%程度にみられるので、非常にありふれたものです。約60-70%では一生に一度しか熱性けいれんをおこしません。通常は特別な検査や定期的な受診は必要としません。ほとんどの場合で脳にダメージを認めず、知能への影響はありません。
6歳以降に、上記と同様の発作を認めた場合にも、熱性けいれんとしての対応でよいとされています。また熱性けいれんをおこしたこどもの中で、約30%程度で複数回の熱性けいれんを認めます。繰り返した場合やけいれんが長い場合(例えば15分以上)には、検査や予防薬などが必要になる場合がありますので、WEPiLiの姉妹サイト「はじめてのてんかん」をご参照ください。

熱性けいれんの種類
熱性けいれんで最も多いパターンは、「かぜなどの発熱に伴い、全身が左右差なくがくがくするもので、数分程度で自然に止まるもの」です。
一方、「15分以上の長い発作」「目だけ、体の一部だけ、右半身だけ、左半身だけ(焦点発作の要素)」「24時間以内に複数回(一発熱機会内)」の、どれか1項目でも当てはまる場合は、「複雑型熱性けいれん」と呼ばれています。1項目も当てはまらないものを「単純型熱性けいれん」と呼んでいます。
また熱性けいれんにおいて長時間持続する発作、または複数の発作でその間に脳機能が回復しないものは「熱性けいれん重積状態」と呼ばれています。「30分以上」とされることが多いですが、5分以上持続していると、薬物治療が必要であることから、「5分以上」とする場合もあります。
けいれん時の対応
対応にはいくつかの注意点(発作中にできればやっておきたいこと、絶対にしてはいけないこと)があります。
詳しくはけいれん発作時の対応のページをご覧ください。
けいれん時の対応
「できればやっておきたいこと」と「絶対にしてはいけないこと」の二つに分けてご紹介します。1. 発作中にできればやっておきた…
病院の受診について
通常「けいれん」「ひきつけ」などの発作は数分以内に自然に収まることが多いので、ほとんどの場合で救急受診は必要ありません。
ただし、「15分以上の長い発作」「目だけ、体の一部だけ、右半身だけ、左半身だけ(焦点発作の要素)」「24時間以内に複数回(一発熱機会内)」の、どれか1項目でも当てはまる場合は、熱性けいれん以外の病気の可能性があり、検査や治療が必要になる場合があるので、救急受診か小児科を受診する方がよいでしょう。
その際は、できればその動きの動画を記録しておいてください。
発作を冷静に観察するのは難しいことですが、医療者が発作を目撃することができるケースは非常に少なく、発作時に介助した方の目撃情報が治療に直結する場合があるので大変重要です。
▶参考:発作時の記録方法と動画の撮り方は?
▶参考:専門外来の受診の仕方
【関連のQ&A】
けいれんで救急車を呼んだ時、搬送先の医師に必ず伝えた方がいいことはありますか?
熱性けいれんの原因
熱性けいれんで最も多いパターンは、「かぜなどの発熱に伴い、全身が左右差なくがくがくするもので、数分程度で自然に止まるもの」です。
詳しいことはまだわかっていません。発熱をきたす感染症は何でも熱性けいれんが起こりますが、特にインフルエンザ(インフルエンザウイルスの感染)や突発性発疹(HHV6やHHV7の感染)の経過中に生じることが多いです。一方、家族や親戚のなかに、「こどものときに同じような熱性けいれんがあった」など熱性けいれんの既往がある場合も少なくありません。
神経細胞の表面にある、NaチャネルやGABA受容体などの神経伝達に関連した設計図(遺伝子)にすこし変化が認められる、などの報告もあります。
熱性けいれんに関する検査
一般的には、問診を行い、その経過が「単純型熱性けいれん」でまず間違いない場合は、特に緊急の検査は必要ありません。さらに緊急治療も必要ありません。
一方で、意識状態が悪い、脱水がある、などの場合は、状態に応じた検査や治療が必要になります。「複雑型熱性けいれん」「熱性けいれん重積状態」の一部では、脳炎・髄膜炎(脳やその周囲に細菌やウイルスが感染すること)の可能性があるため、血液検査、髄液検査、頭部CT・MRI、脳波検査などが必要になる場合があります。
予防について
熱性けいれんは予防する方法があります。
発熱時にジアゼパム(商品名:ダイアップ)を使用する方法です。持続時間が長い発作があった場合、2回以上反復した場合などで、ジアゼパムによる熱性けいれんの予防を検討します。発熱が続いている場合では、8時間後に同じ量の坐薬を使用します。そうすると1回目に使用してから24時間は発作を抑制する効果が続きます。
しかし、ジアゼパムで予防をしたにもかかわらず、熱性けいれんが複数回生じた場合や持続時間の長い発作が生じた場合などでは、抗てんかん発作薬の毎日の内服が薦められる場合があります。
例えば、高潮(熱により発作が起きようとする状態)に対して、土のうを積む(ジアゼパム坐薬でしのぐ)、仮説堤防を立てる(抗てんかん発作薬の内服)ようなイメージです。
予防はいつまでつづけるのか
神経細胞が年齢とともに発達し、熱に対して強くなるため、徐々に熱性けいれんの頻度は減少します。特に6歳以降では随分下がります。
最終の熱性けいれんから、1ー2年もしくは4ー5歳頃まで続けることが薦められていますが、状況によります。
後遺症の可能性
熱性けいれんは直接治す手段はありませんが、大部分が“治癒”します。稀に、熱性けいれん重積時に「海馬」と呼ばれる脳の記憶を生み出す構造が傷ついてしまい、後にてんかんの原因となることがあります。またウイルス感染時に熱性けいれん重積状態となり、けいれん重積型(2相性)急性脳症と呼ばれる急性脳症に罹患し、後遺症を残すことがあります。
以上から、熱性けいれんが重積状態(発作が長く続くこと)にならないようにすることが大切と考えられています。
てんかんの可能性

熱性けいれんのあるこどもでは、後にてんかん(熱など誘因がなく、けいれん発作などの発作を繰り返す状態)がでてくる場合があります。
てんかん発症の頻度は、単純型熱性けいれんでは1%、複雑型熱性けいれんでは2ー7.5%(てんかんの家族歴や神経系の異常があれば高くなる)と言われています。逆にいうと、90%以上でてんかんを認めないともいえます。
しかし、まれにてんかんの初期症状であることがあり注意が必要です。
見分け方については以下の表を参考にしてみてください。

てんかんの情報については、WEPiLiの姉妹サイト「はじめてのてんかん」でご覧いただけます。

熱性けいれんに関連するQ&A
2回目の熱性けいれんが起きた時は、クリニック(小児科)の受診で良いのでしょうか?
熱性けいれんは、通常、数分以内に自然に収まることが多く、ほとんどの場合で救急受診の必要はありません。2回目の熱性けいれ…